
ダイビングをしたことのある方で、多くの方が最初につまずくのが“耳抜き”です。耳抜きが上手にできないとおっしゃる方に話を聞いてみると、
- 体験ダイビングやダイビング講習の際に説明されたけど、よく理解できなかった
- 耳抜きに失敗して痛い経験をして以来、ダイビングをするのに抵抗がある
- 他の人はスムーズにできているのに私だけできなくて毎回焦ってしまう
- 耳抜きが出来るときと出来ないときの差が激しい
など様々な意見をお伺いします。一度苦手意識がついてしまうと耳抜きだけでも大きなストレスになってしまい、ダイビングを躊躇してしまう方も少なくありません。
今回は年間600人以上の体験ダイビングやファンダイビングを担当させていただく現役ダイビングインストラクターが、初心者の方にも解りやすい耳抜きの方法やコツ、耳抜きが苦手な方におすすめのグッズをご紹介いたします。
グッズやコツなどを先に知りたい方は、目次から耳抜きの方法やおすすめグッズなど各項目にとんで記事を読むことができます。
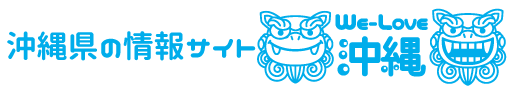




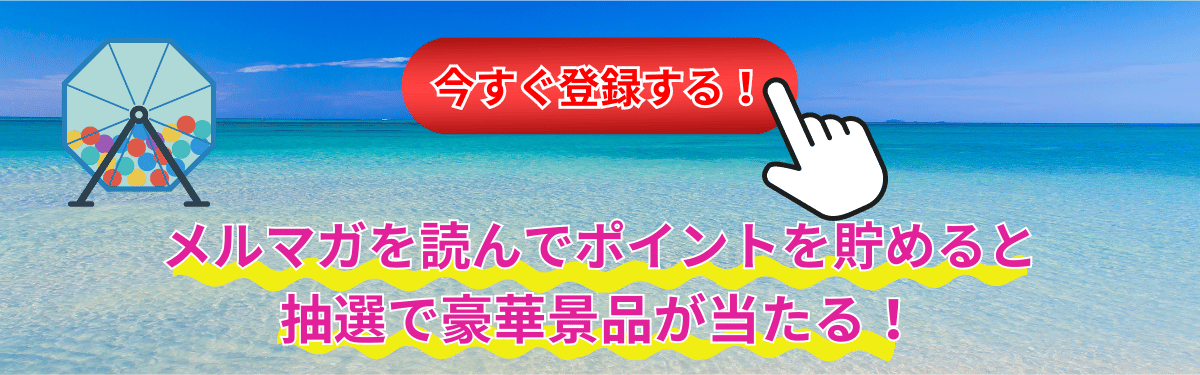







コメント