解体した窯の瓦礫から生まれる「にんじん」
前回、瓦礫が運ばれていった登り窯入口付近の広場では、再度丁寧に掃き清めて水で流す念入りな掃除が行われていました。
これは、石灰石が入り込むのを防ぐため。石灰石は火を入れた際に膨張して爆ぜ、窯の破損の原因になってしまうのだそうです。





広げた瓦礫は、油圧ショベル(パワーショベル/ユンボ)で細かく砕かれます。

ショベルの平らな部分を使い、少しずつ押しつぶすようにして行われる作業。


人の頭ほどの大きさの瓦礫が、みるみるうちに砂時計の砂のようなパウダー状になっていきます。
広範囲の地面を掘ったり土砂をトラックに移動させたりといったイメージが大きい油圧ショベルでの繊細な仕事には、目をみはるばかりでした。
大ベテランの職人さんで、その方にしかできない仕事なのだと聞いて心から納得。
見ている限り降りて様子を確かめるようなこともなく、淡々と、確実に進められる職人技でした。9:30頃から14:00過ぎまでの間に、瓦礫の山はほとんど砂山に姿を変えています。

「にんじん」の成形
パウダーになった瓦礫と原土、わらを混ぜ、粘土状にしたものがこちら。

木の板と枠を使い、「にんじん」を作ります。

適当な大きさの粘土を取り、丸めて板の上へ。細長く成形し、枠に合わせて形を整えます。




陶工たちの手袋はすぐに水分を含んで重く冷たくなっている様子。
作業は2カ所に分かれて行われ、鍬やスコップで一輪車に載せた土を運ぶ場面もありました。



成形されたばかりのにんじんはベニヤ板を噛ませたパレットに積まれます。
水分が多く粘性の高い土なのでかなりやわらかく、形が変わってしまわないよう慎重に取り扱われていました。



1段に載るにんじんの数を数えてみたところ、だいたい66本。陶工10数人で30段分ほどできたということだったので、1日あたり約1980本が作られる計算です。
「にんじん」の乾燥・再成形
にんじんは3段ごとに運ばれ、6段まで重ねて倉庫に保管。しっかりと乾燥させるまでには約2週間が必要だそうです。



数日後のやちむんの里には、トントン、というリズミカルな音が響いていました。
ある程度乾燥が進んだにんじんをたたき締めて形を整え、そのうちの1/3から半分ほどはより先細りに成形し直す作業が行われているのです。



屋根のアーチを作る際、この先細りのにんじんの果たす役割はとても重要。
ブロックのいすとテーブル、厚い羽子板のような大小の道具も使い、膨大な量のにんじんが、にんじんそのもののようなフォルムに整えられていきました。


降り注ぐ太陽の下で乾燥を待つにんじん。

しっかりと乾燥してくると、平置きではなく縦に詰めて保管され、出番を待ちます。


狭間(さま/炎の通り道)や壁の基礎作り
さて、舞台はいよいよ前回基礎部分の一部を残して解体された5番と6番の窯内部へ。レンガやモルタル、様々な道具などが運び込まれていきます。




床面には、まず硅石やメーガニクなどが敷き詰められます。
次に、計測して割り出した窯の中心から耐火レンガを並べます。残っている基礎部分と高さを合わせ、水準器で平衡を取りつつ慎重に進められていました。





レンガに書かれた32、34、36という数字は耐火度を表すもの。数字が大きくなればなるほど耐火度が高くなります。

中心から組んでいくため、残っている壁までの間が微妙に広かったり狭かったりと、一から作る場合にはない大変さも。親方たちも手を貸し、手頃な形のレンガを探したり、新品のレンガを隙間の形に合わせて削って使ったりと、臨機応変な様子がとても印象的でした。







おわりに
基礎部分のレンガ敷きが進められる間、親方たちはL字型の定規(さしがね、かねじゃくなどと呼ばれる工具)と鉛筆でベニヤ板に何かを書き込みつつ相談していました。


結果、出来上がったのはこちら。

この図の中に、窯を長持ちさせるとても大事なポイントが隠れています。
それは何で、いったい何のためなのか、考えてみてください。ヒントは重力。これまでの記事にもたくさんヒントがありますので、お時間のある方は振り返ってみてくださいね。
屋根を作る作業まで出番待ちのにんじんは乾燥のために日向や日陰で干され、広場や通路いっぱいに並んでいることもありました。


もしあなたが北窯でこんな光景を目にしたなら、それは大がかりな窯の修理中ということなのです。工房や窯の周辺を観察して、今どんなことが行われているのかを推測してみる、そんな北窯の楽しみ方も素敵ですね。
次回は狭間を備えた壁の構築。先ほどの質問の答えもしっかりお伝えします。楽しみにお待ちいただけたら幸いです。
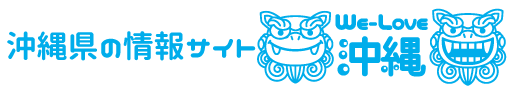

コメント